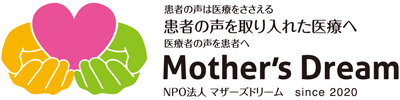2025年3月18日(火)20時~21時
参加者 : 2名
いつものように私の挨拶から始まり、坂村真民先生の「二度とない人生だから」
を唱和し「二度とない人生だから」について、私たちはどう生きていけば良いのか等について語り合いました。
その後、小学校6年生の道徳『お茶の心』の教材について語り合いました。
『お茶の心』
~あらすじ~
秋も終わりに近づいた日曜日、祖母からお茶会に誘われた。祖母はお茶の先生をしているのだ。ハッキリ言ってあまり興味はがなかったけれど、母も参加するという。せっかくの機会だし、私も行くことにした。
「お茶の作法は、四百年ほど前に千利休という人が『わび茶』として完成させたものが始まりで・・・。祖母が参加者の皆さんに説明を始めた。けれども、私には、やっぱり難しすぎて話についていけない。私は、(自分には、ふつりあいなところに来ちゃったなあ。)と思い始めていた。「いろいろと作法はありますけれど、それよりも、まずはお茶を楽しんでください。分からないことがあったら、はずかしがらずに何でも聞いてくださいね。」お茶をいただいている間も、祖母は説明を続けた。祖母の話によると、お茶の席では、もてなす側を「亭主(ていしゅ)」、もてなされる側を「客」とよぶそうだ。このお茶会では祖母が「亭主」をつとめ、わたしや母などは「客」ということになる。お茶のたて方、立ち居振るまいから、わたしたち「客」がどうしたらよいのかを、丁寧に説明しながら進めてくれた。「なぜ、お茶を飲むときに、茶碗を回すのか分かりますか?お茶碗には正面があります。『亭主』がお茶を出す時に、茶碗を回すのは、茶碗の正面を『客』の正面に向けて、見ていただくためなのです。また『客』の側も茶碗を受け取ったら・・・」なるほど、茶碗を回すのにも色々意味があるんだな。亭主も客もお互いに心づかいをしているんだ。お茶と一緒にいただくお菓子も、そのときの季節や相手のかたに合わせて、心をこめて亭主が選ぶらしい。そして、客はまず、お菓子を口にしてから、お茶をいただくそうだ。「あれ、あのお茶碗、今、飲んでいる物とちょっと形がちがう。」祖母が新しく用意した茶碗が目に入り、思わず私はつぶやいた。飲み口が小さい茶碗で、家で使っている湯飲みに少し似ている。「それは『筒茶碗』といって、冬に用いることが多いの。寒い時でも、飲み口が小さいから、お茶が冷めにくいようになっているのよ。」と、祖母が答えてくれた。「そうなんだ。季節によってお茶碗迄変えているんだ。」
「お茶碗だけではないのよ。他の道具も・・・。ほら、そこにかけてあるかけじくも、季節やお客様によって、亭主が『これは』というものを選んで用意するもの。」お茶会って、作法のとおりお茶を飲むだけなのかと思ったら、いろいろと「客」をもてなす準備があるんだ。夏だったら、どんなもてなし方をするんだろう。いろいろ想像してみると、ちょっと楽しくなってきた。初めは、何をどうすればよいのかも分からなかったし、変なことをして他のお客さんに笑われたらどうしよう。なんておもっていたけれど、そんな心配は必要なかったな。お茶に出て、何となくほんわかと温かな気持ちになった。おばあちゃん、ううん、「亭主」さんの細かい心づかいに、ふれられたからなのかもしれないな。
家に帰る間も何だかとてもいい気分だったので、「お母さん、わたしちょっときんちょうしちゃったけど、お茶、本当においしかったね。おばあちゃんに習ってみようかな。」「ふふ、おかしがおいしかったからじゃないの?」「ううん。参加してみて、わたし、人をもてなすという心が少し分かったような気がするの。」わたしは、気になっていたことを母にたずねた。「茶室にかけてあったかけじくの言葉は、どういう意味なのかな。」「ああ、『一期一会』って書いてあったわね。これは、人と人って一生のうちに一度しか会わないかもしれないでしょう。だから、その一度かもしれない出会いの場を、心から大切にしましょうということだったと思うわ。もう少しくわしく調べてみたら?」「出会いを大切にしよう・・・か。うん、調べてみる。」
~学び~ ・ 日本に古くから伝わる茶道。そこにこめられた「お茶の心」とは、どんな心なのでしょうか?
➡ 「もてなす心」
・「わたし」が温かな気持ちになったのは、どうしてかな?
・「もてなす心」とは、どんな心のことをいうのかな?
・お茶会の中にあったような「もてなす心」を、わたしたちの生活の中から見つけて、紹介し合いましょう。
・身近にある伝統文化や、昔からある言葉などの由来について調べ、発表しましょう。
カフェ会を重ねるたびに少しづつではありますが、私達の魂が何ミリかではありますが大きくなるような内容を取り扱っていこうと、思っております。
NPO法人マザーズドリーム 牧原
※サポートメイト(伴走支援)は商標登録済です。